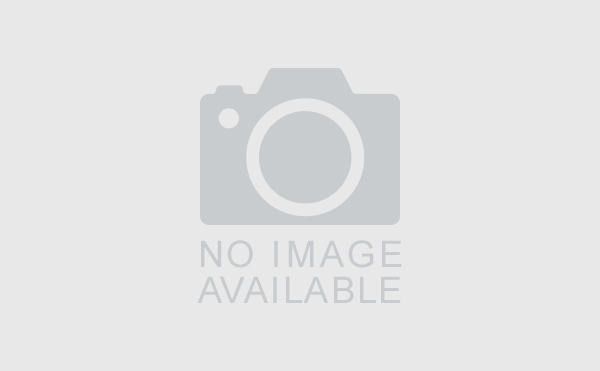六月末は夏越の祓い
神事の年中行事として、今月末は夏越の祓があります。
夏越の祓(なごしのはらい)は、
年に二度、6月と12月末に行われる大祓の、六月に行われるものを指します。
そもそも大祓とは
神社庁によれば、(以下神社庁HPより引用)
大祓は、我々日本人の伝統的な考え方に基づくもので、
常に清らかな気持ちで日々の生活にいそしむよう、自らの心身の穢れ、
そのほか、災厄の原因となる諸々の罪・過ちを祓い清めることを目的としています。この行事は、
記紀神話に見られる伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の禊祓(みそぎはらひ)を起源とし、
宮中においても、古くから大祓がおこなわれてきました。
中世以降、各神社で年中行事の一つとして普及し、現在では多くの神社の恒例式となっています。年に二度おこなわれ、
六月の大祓を夏越(なごし)の祓と呼びます。
大祓詞を唱え、人形(ひとがた・人の形に切った白紙)などを用いて、身についた半年間の穢れを祓い、
無病息災を祈るため、茅や藁を束ねた茅の輪(ちのわ)を神前に立てて、これを三回くぐりながら
「水無月の夏越の祓する人は千歳の命のぶというなり」と唱えます。
また、十二月の大祓は年越の祓とも呼ばれ、
新たな年を迎えるために心身を清める祓いです。
だそうで、
要約すると、
半年間の穢れや罪や過ちを祓い清める儀式となります。
(スポンサーリンク)
本来なら、年末もそういう穢れを祓い清めて、
年が明けたらまた改めて初詣に行くのがいいと思うのですが、
まあそうも言ってられない、大晦日、元旦と忙しい時期に続けて神社に行くのも気がひける、と考えている自分は、年末の大祓はどうしても省略してしまうものの、
夏越の祓は、いつも月初めにお参りしている最寄りの神社に伺います。
夏越の祓いの作法は各神社の作法を確かめて
茅の輪が設置されている神社では、各所によって微妙に茅の輪のくぐり方や回数が異なっているので、
その神社に出向いて作法を確認してからくぐりましょう。
場所も鳥居の前、
境内の参道の途中、様々です。
くぐる回数や、方向などもいろいろです、
説明書きを読んでから列にならんたほうがいいですね。
それから、自分の穢れを半紙などでできた人形(ひとがた)に移すために名前を書いて納めますが、
これも生年月日まで書くところや、年齢を書くところ、名前だけでいいところなど、神社によります。
神事に参加する場合はそれなりに金額がかかります。
(だいたい、他のお祓いや祈願と一緒くらいの目安)
人形のみの領布代がかかるところも。
また、その時だけの御朱印やお守りを出しているところもあります。
(限定なので、すでに配布が終わってしまっているところも続出してますが。)
宗教上で関係ないと思われる人、
別に必要ないと思われる人も多いでしょうが、
このような年中行事を意識するだけでも
半年間の自分の行動を振り返る、良いきっかけになるのではないでしょうか。
ほとんどの神社が祭礼として6月30日に神事を行いますが、
オフィス街近くだと今年は土曜日に当たるので、前倒して29日に行うところもあるようですよ。
これも行きたい神社の動向をよく調べて向かいましょう。
今年の下半期、穢れを祓って、新たに気持ちよく再スタート切りたいですね。
(スポンサーリンク)